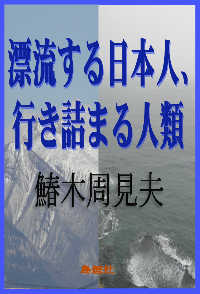ボクシングについて静かに考えてみた
鰆木周見夫(さわらぎ・すみお)
ノンフィクションライター
第2回 ボクシングは人生そのものである
❶観客は自分の人生をリング上のボクサーに投影する
一発パンチで天国から地獄へ落ちた小坂照男の暗転に震えた観客
ボクシングの試合は人生にたとえられる。
一瞬の逆転劇がある。
明から暗へ。そして暗から明へ。試合前に描いた設計図通りにはいかない。
それを、観客は自身の人生にダブらせる。
1964年7月27日、両国の蔵前国技館。
ジュニア・ライト級の世界王者フラッシュ・エロルデ(フィリピン)に挑んだ同級1位の小坂照男は、13連勝中(7KO)の勢いでリングに上がった。未だ日本人によって達成されていなかった中量級でのタイトル奪取。その期待が小坂に託されていた。
試合は、小坂有利で進んだ。
12回、ゴングが鳴ってもエロルデはコーナーから出てこないで、椅子に座ったまま。試合を放棄したのか。小坂は、進み出てエロルデに襲いかかろうとする。小坂のKO勝ちか。
が、その後、信じられないことが起こった。
防戦一辺倒の構えから、一瞬の隙を衝いて放ったエロルデの左フックが小坂の顎をとらえたのだ。
ロープを背にふらつく小坂。
ここぞとばかりに襲いかかるエロルデ。
そこに、レフェリーが割って入って試合を止める。
座布団を投げる観衆。
エロルデと同じフィリピン人レフェリーの判断は正しかったのか。
ボクシングをスポーツと見る限りそれは正しい判断だった。小坂の足は正常さを失っており、試合を続行していれば間違いなくキャンバスに沈んでいただろう。
観客はレフェリーに怒ったのではない。
小坂に同化した自分の人生の暗転に無意識のうちに怒ったのである。
コツコツと努力を積み重ねてきてようやく摑みかけていた夢が、あと一歩のところで打ち砕かれる。
目の前で起きた小坂の一瞬の暗転は、見ている者たちの人生の姿なのかもしれない。それへの無意識のうちの同化が、レフェリーヘの怒りへと転化されたのである。
❷ボクシングにも人生にも逆転勝利はある
ピエロを演じていたガッツ石松はクレバーなボクサーだった
全く期待されていなかったボクサーが予想に反してチャンピオンベルトを奪取する。それも人生である。世間を見返すことができる希望を与えてくれる人生のひとコマである。
1974年4月11日、東京・日大講堂。65戦60勝50KOの世界ライト級王者ロドルフォ・ゴンザレス(メキシコ)に挑んだガッツ石松の戦歴は26勝14KO11敗5分。勝利数よりも負け数と引き分けの数が目立つ石松。誰もが石松に勝ち目はないと思っていた。
それまでの石松で目立っていたのは、リングに登場する際の股旅の三度笠姿だけである。当時では派手なパフォーマンス。さほど強くないボクサーが分不相応な演出をやると、それは滑稽に見える。石松のパフォーマンスはその次元を脱してはいなかった。
当時、石松が所属していたヨネクラジムには、フェザー級世界チャンピオン柴田国明がいた。ハードパンチャーだったが、顎が弱く、毎回、KO勝ちかKO負けかのスリリングな試合を展開しファンを魅了していた。真面目な性格で練習熱心な柴田は、ヨネクラジムの優等生的な存在だった。
その柴田とよく比較された石松。派手なパーフォーマンスで奇をてらっていた石松は、いわばピエロだった。滑稽を演じていたのである。笑われることを承知で。
だが、石松の心の中は熱く滾っていた。俺を笑っている世間を見返してやると燃えていた。
試合は、石松ペースで進み、8回、後に「幻の」と形容されることになる右フックで最強のチャンプをマットに沈めたのである。
石松はクレバーなボクサーである。多くの敗戦を糧にしてきたという意味において。石松は3度目の世界挑戦でベルトを獲得した。
最初は1970年1月パナマでイスマエル・ラグナ(WBC)に挑戦して13回KO負け。2度目は1973年9月、同じくパナマで「石の拳」ロベルト・デュラン(WBA)に10回KO負け。この経験は大きかった。見方は変えれば、あのデュランに10回まで倒れなかったという評価もできる。
しかし、誤解を恐れずに触れれば、石松のクレバーなところは、10回に食らったボディーブローで無理に起き上がらなかったところにある。石松は、この回だけですでに2回のダウンを喫しており、その2回ともボディーブローによるものだった。パンチは効いていたのだろうが、それでもスムーズに起き上がっている。そして3度目のダウン。このダウンも、先の2回と同様に起き上がれるくらいのスタミナは残っているようにも見えた。
だが、石松はファイティングポーズをとらなかった。石松なりの計算が働いたのではなかったか。後年、石松自身もそれを肯定する言葉を漏らしている。多少の負け惜しみもあるのだろうが、石松自身の思いのなかにあえて起き上がらなかった正当性を宿していたのだろうことは間違いない。
もし起き上がっていたら、致命的なパンチを食らって石松のボクサー人生も終わっていたかもしれない。当時の「石の拳」はそれほどに最強であった。
起き上がらずに次のチャンスを待ち、それをものにした石松。そして、その後はチャンピオンとして4度の防衛に成功した。
トレーナーのエディ・タウンデントは石松のことを「チャンピオンになってから強くなった選手」と評している。
引退後は俳優に転身、石松は相変わらずピエロを演じているが、ピエロはクレバーな人間でなければ演じられないのである。
最近、石松のことを新聞記事で読んだ。
東日本大震災で被災した福島県飯館村の人たちが避難生活を送っている栃木県鹿沼市の総合体育館を、3月31日、石松が水、米、納豆など大量の食料を持って訪れ、避難者を激励したという記事。
鹿沼市は、石松の出身地。そして石松の妻の実家が、津波の被害を受けた岩手県大槌町で、親戚にはまだ行方のわからない方もいるということだった。
❸あと一歩のところでベルトが逃げていく「人生の不条理」
村田英次郎の悲劇──世界挑戦4度のうち2度の引き分け
何が足りなかったのか。引き分け。僅差の判定負け。勝負はどちらに転んでもいいほどの試合。しかし、勝利の女神は自分には微笑まなかった。それも人生、といってしまえばあまりにも酷な話になる。
バンタム級の村田英次郎は悲劇のボクサーだった。世界タイトル挑戦4度。そのうち初挑戦の対ルペ・ピントール戦と2戦目の対ジェフ・チャンドラー戦が引き分け。
強豪ひしめく黄金のバンタム級。相手はいずれも最強のチャンプ。勝っていれば、村田は誇り高い世界チャンピオンの栄誉に浴することができたはずだった。
しかし、勝利はほんのわずかな指の間からこぼれ落ちていった。試合に負けたわけではないが、ベルトは奪取できなかったのである。
何が足りなかったのか。それを指摘することは難しい。ただ、確実に言えることは、チャンピオンとそうではないボクサーとでは、その後に受ける待遇、名誉には天と地ほどの差があるということである。
世界戦初挑戦の対ピントール戦。10ラウンド、マウスピースをつけるのを忘れて出てきたピントール。ピントールがそのマウスピースをはめなおす際に一瞬の隙を見せた。しかし、村田はその隙をあえて狙わなかった。
ある雑誌のインタビューで、そのときの心境を訊かれた村田はこう答えている。
「あのとき? 打ちこめばいいんだろうけど気が乗んなかったんだな。待とうと思ったんじゃないよ。自然にそうなっただけ。チャンピオンになれなかったのは、甘かったからかもしれない。もう少し荒っぽい気持ちがあったらよかったと思うこともある。いい子ブリッコ。はがゆいよね、自分で」
往年の世界ヘビー級チャンピオン、ジョー・ルイスにもそういうエピソードが残っている。
1951年5月22日。ルイスに挑戦したのは、闘争心旺盛なアイルランド系のビリー・コン。ライト・ヘビー級チャンピオンだったが、階級を上げてルイスに挑んだのだ。
試合は、一進一退。だが、流れは次第に挑戦者コンがリードする展開になった。エンジンをかけなければベルトを奪われるルイスは、10回、コンをロープに追いつめる。そのとき、一瞬、コブが右足を滑らせてバランスを崩した。ルイスのチャンスだった。ルール上は、相手を攻撃してもいいケースである。しかし、ルイスはそうはしなかった。
「ジョー・ルイスの生涯」を書いたクリス・ミードは、次のように触れている。
「そうするかわりに、ルイスはうしろにさがり、コンがバランスを取り戻すまで待った。ルイスは習慣で反応してしまったのだ。これまで相手が足を滑らせたときに殴ったことは一度もなかった。ブレイクするときもそうだったし、汚い手はつかわなかった。ルイスの態度はあっぱれなスポーツマンぶりを示したが、同時にルイスの自信の深さでもあった。自分の不利なときでさえ、ルイスは決して落ち着きを失わなかったし、コンのスリップにつけこむような姑息な態度を取ることもなかった」
11回、12回もコン優位で進み、このままいけばコンの判定勝ちも現実になるはずだった。しかし、そうはならなかった。コンのセコンドは残りのラウンドを慎重に闘うように指示したが、コンは偉大なチャンピオンをKOできると考えた。そうすれば、勝利にさらに箔がつく。
それが裏目に出た。
13回、コンはルイスのパンチを浴びてマットに沈む。
摑みかけていた勝利が手のひらからするりとこぼれ落ちてしまったのである。
コンのマネージャーが語っている。
「もし彼がアイルランド人でなくユダヤ人の頭をもっていたなら、彼はチャンピオンになれただろう」
いや、そんな問題では決してない。リングの上では、もっと次元の違う何かがボクサーの精神に影響を及ぼしているのではないだろうか。
それは、闘った者にしかわからない、しかも言葉にはあらわせない聖なるものなのかもしれない。
❹勝つためには、練習はもとより戦略が必要である
ボクシングを科学に近づけたパイオニア、トミー・ローランド
対戦相手の癖を、ビデオやその他の情報を駆使して分析する。相手の長所短所を知り尽くし、弱点を正確につく作戦を立てて試合に臨むのは、今ではごく当たり前の話になっているが、そんな戦略行動を実践したパイオニアとして知られているのが、トミー・ローランド。1927年から29年にかけてライト・ヘビー級のチャンピオンだったボクサーである。
アメリカのある作家は、彼がボクシングを「文字通り、科学へと近づけた」ボクサーだとして、こう記している。
「彼は──タニー同様に──対戦相手のスタイルを研究し、現代のボクサーやトレーナーなら、ごく当たり前にやるように、試合ごとに詳細な戦略を立てた。ローランドは、地下室に鏡を置き、トレーニング中の自分の姿を見られるようにした。というのも、彼自身言っているとおり、対戦相手の目に映る自分の姿を見たことのあるボクサーはいないからである」
対戦相手を、というよりボクシングそのものを最も研究していたのは、カス・ダマトが生きていた頃のあのマイク・タイソンである。
ダマトは、1910年代からボクシングの試合のフィルムを1万本を超える量で所有していた。タイソンは、毎晩そのフィルムを見て研究していた。当時のタイソンの趣味は、飼っていた鳩の世話とボクシングのフィルムを見ることだったのだ。
ダマトの教えを忠実に守っていた頃のタイソンは強かった。それは、ボクサーもひとりの人間であり、精神的に支えてくれる人物の有無がリング上での闘いにも大きく影響することを物語っている。
偉大なボクサーの側には偉大な人物が影のように寄り添っているものなのである。
❺リング外の闘いに苦しんだ王者たち
カス・ダマトに先立たれたマイク・タイソンの悲劇
マイク・タイソンのボクサー人生は、カス・ダマトの死によって暗転していく。人生には、亡くしてしまって初めてその尊さに気づくものが多々ある。タイソンにとってのダマトはまさにそんな存在ではなかったか。
1908年ニューヨーク生まれのダマトは幼い頃からボクシングに関心を抱いていたが、12歳のときの大人との喧嘩で片目の視力を失っていた。その後22歳のときから若いボクサーの指導を始め、フロイド・パターソン(ヘビー級)やホセ・トーレス(ライト・ヘビー級)らの世界チャンピオンを育て上げている。
少年院で更正中だったタイソンをカス・ダマトに会わせたのは、保護司のボビー・スチュワート。スチュワートは元はアマチュアのボクサーだった。
ダマトは、タイソンの動きから即座にその才能を見抜いたといわれるが、真偽のほどは定かではない。ともかくも、ダマトはタイソンを引き取り、自分の手元に置いてボクシングの手ほどきを行っていく。タイソンにとって大きかったのは、ダマトから「人間としての心」と「ボクサーとしての心構え」を教えられたことだろう。
タイソンはこう語っている。
「カスは、オレの親父、いや、親父以上だった」
「父親を持つことはできる。でも、それが、なんだって言うんだ。実際にはなんの意味もないことさ。カスは、オレの背骨(バックボーン)だった。すべてを、オレを最もいいようにやってくれた。オレたちは、いつもいっしょに過ごし、いろんなことを話した。二人で話したことが、あとになってオレにかえってくるんだ。性格とか、勇気とか、についてね。英雄や臆病者についても話した──英雄も臆病者も同じことを感じる、だが、英雄は、自分の恐怖心を利用し、それを対戦相手に投影する。一方、臆病者は逃げる。同じ恐怖心だが、それをどう使うかってことさ」
ダマトは、実の親父以上の精神的支柱だったのである。
だから、彼を信じて安心してボクシングに打ち込むことができた。
しかし、ダマトの死後、タイソンは徐々に、リング外の些末な出来事への対処に追われるようになる。リング外の人生で苦戦を強いられていくのだ。
相手は、殴り倒せばいいという類のものではない。世渡りに慣れた手練れに若いタイソンが太刀打ちするのは難しかったのだ。その影響がリング上の試合でも出始める。
やがてダマトの財産が燃え尽き、タイソンは転落していく。
ボクサーがリング外の闘いに悩み始めると必ず試合に影響が出る。悩みの原因の多くは金と家族の問題である。
ヘビー級のタイトルマッチではとてつもない大金が動く。ダス・カマト亡き後、そして結婚してからのタイソンは、マネジメント契約の問題で心身を消耗した。そこに結婚後の家族が絡み、さらに消耗した。ボクサーにとって、信頼できる人間が側にいることがいかに大事かということを物語っている。
気が付いてみると実質的に入ってくるファイトマネーが少ない。気づいても契約上、さらに先まで闘わなければならない。そのことを知ったボクサーの戦意喪失は火を見るより明らか。
日本のファンが我が目を疑った東京での防衛戦、プロ入り後初めて敗れる前のタイソンがそういう状況だった。そして、タイソンをめぐる状況はますます悪化していく。もし、タイソンに、リング上の闘いに専念できる態勢が整っていれば、タイソンの時代はもっと長く続いていただろうことは想像に難くない。
世界で最も強いボクサーもリングを降りれば20代の若者に過ぎない。社会生活を営むのに必要な知識を完璧に備えているわけではない。契約条項の解釈、ファイトマネーの分配、税金の問題等々。真にボクサーのことを思っている人間が防波堤とになって処理していなければ、無知な若者はたちまちのうちに、手練れの金の亡者たちに食いつぶされてしまうのである。
ダマトを失ったタイソンは、リングの外ではあまりにも無防備だったのかもしれない。